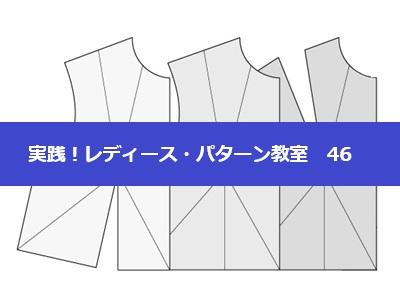
No.046 パターンの基礎(その4)ダーツに関するあれこれ
実践!レディース・パターン教室 著:菊地 正哲
- 学習・知識
アパレル工業新聞 2024年9月1日発行 4面
この記事・写真等は、アパレル工業新聞社の許諾を得て掲載しています。
今回はタイトル通り正真正銘の基礎、ダーツに関するあれこれです。そもそもダーツとは何ですか?ダーツとは、平面の布を曲面化するために布の一部をつまんで縫い取ったものです。からだに沿った服を作るのに欠かせないものですね。そんなこと分かっとるわいと仰らずに、そのダーツというものについて改めて考えてみましょう。たかがダーツと笑うなかれ、普段考えたこともなかった何かが見えてくるかも知れませんよ。
1.ダーツ展開の基本、『回分集移』とは?
まずはダーツ展開の基本のおさらいである。『回分集移(かいぶんしゅうい)』とは何か?これはダーツ展開における4つの基本操作のことで、『回』は回転、『分』は分散、『集』は集約、『移』は移動のことである。パターン設計におけるあらゆるダーツの展開は、この4つの操作の中に含まれる。では、1つずつ解説していこう。
●ダーツの回転
【1-1】ダーツは、ダーツの頂点を基点として360度どの方向にも回転することができる。1本のダーツを複数方向に振り分けて展開することもできる。パターンの面積は変わらない。
![実践!レディース・パターン教室46[1-1]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-1.jpg)
●ダーツの分散
【1-2】1本のダーツを2本、もしくはそれ以上にする。ダーツの本数とはダーツの頂点の数のことであり、分散とはダーツの頂点の数を増やすことである。展開によってパターンの一部に重なりや空隙が発生し、パターンの面積は若干変化する。本数を増やせばギャザー展開にもなる。
![実践!レディース・パターン教室46[1-2]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-2.jpg)
●ダーツの集約
【1-3】2本、もしくはそれ以上のダーツを1本にする。集約とは、複数あるダーツの頂点の数を1つにすることである。集約する位置は、必ず元のダーツとダーツの内側でなければならない。こちらも展開によってパターンの面積は若干変化する。
![実践!レディース・パターン教室46[1-3]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-3.jpg)
●ダーツの移動
【1-4】ダーツの本数を変えずに、ダーツの頂点の位置を移動する。移動先のダーツの頂点との中間を起点に元のダーツをたたむ。元のダーツと移動先のダーツの折り山には段差が出来るので、段差をなくすように折り山を引き直す。
※このダーツの移動だけ他の展開とは性質が異なる。回転、分散、集約は、基本的に元のシルエットを変えずにダーツの形態だけを変化させるものだが、移動はシルエットの変化が伴う。
![実践!レディース・パターン教室46[1-4]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-4.jpg)
【1-5】これは移動か?
元のダーツと移動先との間を細かくスライスして小さなブロックに分割する。各ブロックをスライドして元のダーツとの隙間を埋める。”面積移動”とも呼ばれる操作だが、主にジャケットのパネルラインの移動などに使われることがある。この展開だと、理論上どこまで移動してもシルエットは変化しないことになり、パターンの展開原理と矛盾する。展開をしている気分にはなるが、これではダーツを消しゴムで消して引き直したのと同じことである。これは移動とは言えない。
![実践!レディース・パターン教室46[1-5]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-5.jpg)
2.曲面と立体の違い
ダーツとは、平面の布を曲面化するために布の一部をつまんで縫い取ったものであるが、では曲面とは何だろう?数学や幾何学では曲面に対して難しい定義があるが、ここではあくまでシンプルに「どこにも直線が存在しない面」としておく。よく立体化という言葉を使うことがあるが、立体は体積を伴う閉じた図形のことであり、多面体など二次元の面を組み合わせた図形も含まれるので、正確には立体化ではなく曲面化が正しい。
●球体の平面展開
【2-1】地球儀を平面展開した図。
グレーで塗りつぶした部分がダーツとなる。正確にはこの平面図を組み立てても完全な球体にはならない。展開面を細かくするほど球体に近づくが、永遠に完全な球体にはならない。逆を言えば球体を平面に展開することはできないことになる。これを衣服に置き換えると、ダーツは縫うだけでは布を曲面化することはできず、布の伸縮(アイロン操作)があってはじめて曲面になるのである。
![実践!レディース・パターン教室46[2-1]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-6.jpg)
●円錐の平面展開
【2-2】円錐を平面展開した図。
これは図形上に直線が存在するので曲面ではない。この面を錘面(すいめん)と言うのだが、同じような性質の面として柱面(円柱)などもある。このような平面を伸縮させないでできる平面ではない面を可展面と言う。衣服の基本的な造形においては存在しない面なので、このことからもダーツはただ縫うだけではなく、アイロン操作による布の伸縮が必要なのが分かる。
![実践!レディース・パターン教室46[2-2]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-7.jpg)
3.ダーツの形状
ここまで例に挙げたダーツはすべてくさび型の三角ダーツだが、他にもいろいろな形状のダーツがある。中には縫い合わせたときの曲面の形状が想像できないものもあるので、いくつか紹介する。
●三角ダーツ
【3-1】ダーツの基本形。言うまでもなく平面を曲面化するための縫い取り分で、左右の長さが同じであることが基本。
【3-2】縫い目をアウトカーブにしたダーツ。直線のダーツだとダーツ止まりが突出してしまう場合に用いる。頂点の角度をゼロに近くすることで突出のない丸い面を作る。
【3-3】縫い目をインカーブにしたダーツ。しゃくれたシルエットを作るときに用いる。頂点の角度が広いので、ダーツ止まりは突出した形になる。
![実践!レディース・パターン教室46[3-1]~[3-3]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-8.jpg)
●ひし形ダーツ
【3-4】ダーツの頂点が上下2か所あるダーツ。ダイヤダーツとも言う。主に上着のウエストを絞るときに用いる。左右の形が対象であることが基本。ガーブになったものはフィッシュダーツと言う。
![実践!レディース・パターン教室46[3-4]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-9.jpg)
●五角形のダーツ
【3-5】ひし形ダーツの頂点の一方を布端まで伸ばし、間口を開けたダーツ。これも主に上着のウエストを絞り、更に裾回りも詰めるときに用いる。
![実践!レディース・パターン教室46[3-5]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-10.jpg)
●変形ダーツ
【3-6】三日月形ダーツ。三角ダーツの変形だが、左右のカーブは相似形で長さは同じ。カーブの度合いによってはデザインとして用いることがある。縫製は困難である。
【3-7】ひし形ダーツの左右非対称型。左右の長さが異なるので縫製は困難を極める。更に、長い方をいせ込むか短い方を伸ばすことになり、「インカーブは伸ばす、アウトカーブはいせる。」という縫製の大原則に反する。現実的には衣服設計における整合性もなければ必要性もない。
![実践!レディース・パターン教室46[3-6][3-7]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-11.jpg)
【3-8】星形のダーツ。ひし形ダーツのタテとヨコを組み合わせたもの。縫ったときの形状を想像できるだろうか?実際に使うことがあるのかどうか分からないが、使うとしたら衣服のどの部分に用いるのか、考えてみるのも面白い。
【3-9】これはもはやダーツではない。穴の開いた生地の補修である。あるとすれば、生地に絞り加工をしたように見せる効果があるくらいか。
![実践!レディース・パターン教室46[3-8][3-9]](/shared/images/community/column_kikuchi_46-12.jpg)
次回は、ダーツのアイロン処理と地の目の関係についてあれこれ述べる。



