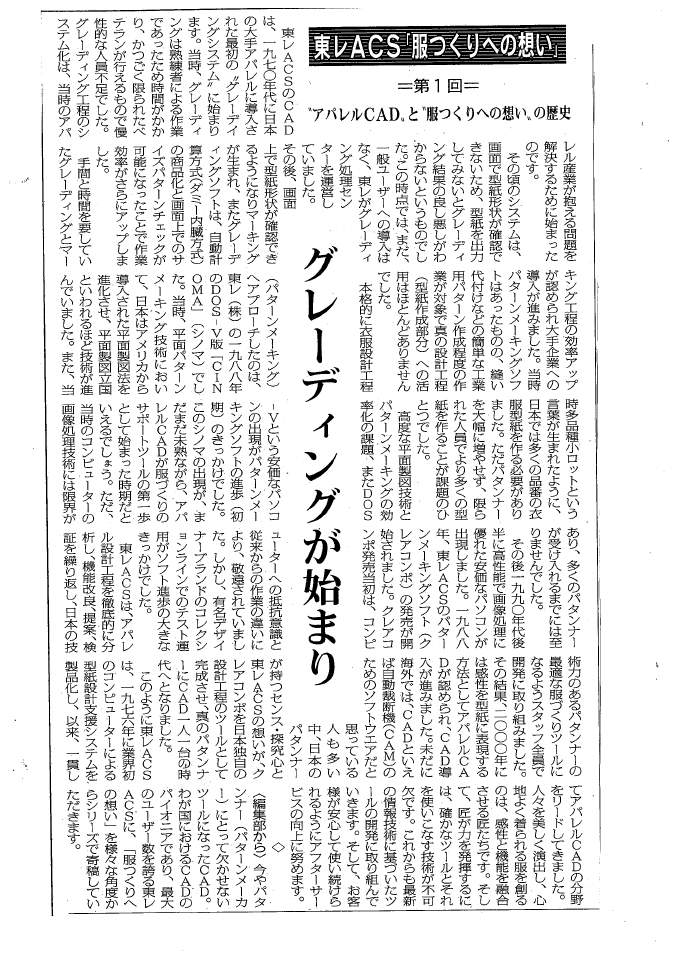2015年10月1日 アパレル工業新聞掲載
東レACS「服つくりへの想い」=第1回="アパレルCAD"と"服づくりへの想い"の歴史
東レACSのCADは、1970年代に日本の大手アパレルに導入された最初の"グレーデイングシステム"に始まります。当時、グレーディングは熟練者による作業であったため時間がかかり、かつごく限られたベテランが行えるもので慢性的な人員不足でした。グレーディング工程のシステム化は、当時のアパレル産業が抱える問題を解決するために始まったのです。その頃のシステムは、画面で型紙形状が確認できないため、型紙を出力してみないとグレーディング結果の良し悪しがわからないというものでした。この時点では、まだ、一般ユーザへの導入はなく、東レがグレーディング処理センターを運営していました。その後、画面上で型紙形状が確認できるようになりマーキングが生まれ、またグレーディングソフトは、自動計算方式(ダミー内蔵方式)の商品化と画面上でのサイズパターンチェックが可能になったことで作業効率がさらにアップしました。手間と時間を要していたグレーディングとマーキング工程の効率アップが認められ大手企業への導入が進みました。当時パターンメーキングソフトはあったものの、縫い代付けなどの簡単な工業用パターン作成程度の作業が対象で真の設計工程(型紙作成部分)への活用はほとんどありませんでした。
本格的に衣服設計工程(パターンメーキング)へアプローチしたのは、東レ㈱の1988年のDOS-V版CINOMA(シノマ)でした。当時、平面パターンメーキング技術において、日本はアメリカから導入された平面製図法を進化させ、平面製図立国といわれるほど技術が進んでいました。また、当時多品種小ロットという言葉が生まれたように日本では、多くの品番の衣服型紙を作る必要がありました。ただパタンナーを大幅に増やせず、限られた人員でより多くの型紙を作ることが課題のひとつでした。高度な平面製図技術とパターンメーキングの効率化の課題、またDOS-Vという安価なパソコンの出現がパターンメーキングソフトの進歩(初期)のきっかけでした。このシノマの出現が、まだまだ未熟ながら、アパレルCADが服づくりのサポートツールの第一歩として始まった時期だといえるでしょう。ただ、当時のコンピュータの画像処理技術には限界があり、多くのパタンナーが受け入れるまでには至りませんでした。その後1990年代後半に高性能で画像処理に優れた安価なパソコンが出現しました。1998年、東レACSのパターンメーキングソフト(クレアコンポ)の発売が開始されました。クレアコンポ発売当初は、コンピュータへの抵抗意識と従来からの作業の違いにより、敬遠されていました。しかし、有名デザイナーブランドのコレクションラインでのテスト運用がソフト進歩の大きなきっかけでした。
東レACSは、アパレル設計工程を徹底的に分析し、機能改良、提案、検証を繰り返し、日本の技術力のあるパタンナーの最適な服づくりツールになるようスタッフ全員で開発に取り組みました。その結果、2000年には感性を型紙に表現する方法としてアパレルCADが認められ、CAD導入が進みました。未だに海外では、CADといえば自動裁断機(CAM)のためのソフトウエアだと思っている人も多い中、日本のパタンナーが持つセンス・探究心と東レACSの想いが、クレアコンポを日本独自の設計工程のツールとして完成させ、真のパタンナーにCAD一人一台の時代へとなりました。
このように東レACSは、1976年に業界初のコンピュータによる型紙設計支援システムを製品化し、以来、一貫してアパレルCADの分野をリードしてきました。人々を美しく演出し、心地よく着られる服を創るのは、感性と機能を融合させる匠たちです。そして、匠が力を発揮するには、確かなツールとそれを使いこなす技術が不可欠です。これからも最新の情報技術にもとづいたツールの開発に取り組んでいきます。そして、お客様が安心して使い続けられるようにアフターサービスの向上に努めます。